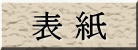
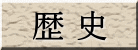
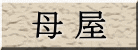
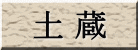
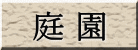
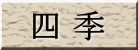
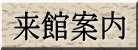
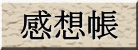
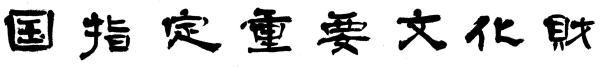  
|
| |
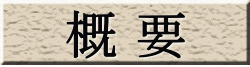 |
|
|
|
| |
渡邉邸は、酒造業・廻船業・大名貸し・新田開発で財を成した豪農・豪商の大邸宅。500坪の母屋・6つの土蔵・名勝庭園など、随所に往時の風格を偲ぶことが出来ます。
|
|
| |

|
現在の母屋は、江戸時代末期の文化14年(1817)に再建されたもの。豪壮な梁組と吹き抜けの土間が壮大な空間を造り出し、訪れる人を圧倒します。部屋は約40室あり、風呂4か所・便所7か所を備えています。
最盛期には75人の使用人が「現場」と「帳場」に分かれて働き、1,000ヘクタールの山林を経営、700ヘクタールの耕地から9,000俵の米を収納したといいます。 |
|
| |
昭和29年(1954)に国の重要文化財に指定されましたが、屋根を内側から煙で燻すために、今でも囲炉裏で火を焚いています。
母屋の屋根は、杉の薄板の上に玉石を置いて押える「石置木羽葺屋根(いしおきこばぶきやね)」という日本海側特有の工法。約22万枚の板と15,000個の石を使用しており、日本最大規模を誇ります。
|

|
|
| |

|
大座敷から臨む遠州流の池泉回遊式庭園は、江戸時代中期に作庭されたもの。
昭和26年に庭匠田中泰阿弥が修復を手掛け、石組の見事さはこの道の極みに達すると言われています。
昭和38年(1963)国の名勝に指定されました。 |
|
| |
旧米沢街道に面した3,000坪に及ぶ敷地は、その周囲に黒塀と外堀をめぐらせており、母屋・名勝庭園の他に、米蔵・味噌蔵・金蔵・宝蔵・裏土蔵・新土蔵の6棟が今も残っています。
映画やテレビドラマの撮影でも度々使用されており、平成7年にNHKで放送されたドラマ「蔵」(原作:宮尾登美子)は根強い人気があります。 |

|
|
| |
 |
|